ジュニア世代の各チームで皆さん観たときや練習したことがあるのではないでしょうか?
サッカーのドリブルの練習を行う上で、マーカーやコーンを使ったドリブル練習は賛否両論があるかとは思いますが、私は有効だと思います。
否定的な意見としては、
- 動かないコーンでやっても意味がない(相手は動く)
- 判断が必要ない状況で練習をしても意味がない
といったものがあります。
つまりサッカーの試合における状況と動かないコーンの状況が乖離しているということです。
しかし、それはコーンドリブルの目的が「試合で相手を抜くこと」に比重を置いてあるから上記の結果になってしまうのだと思います。
例え工夫して不規則にコーンを置いたとしても結果はそこまで変わらないでしょう。
目的を「相手を抜く」のではなく、「ボールコントロールの向上」「身体の使い方の向上」に設定すればコーンドリブルを行うことで素晴らしい結果(サッカーが上手になる)へとつながっていきます。
尚、現在ではこういった考え方が主流になりつつあり、以前までは否定的な意見の方も考えを変えてきているみたいです。
かつてFCバルセロナの現地スクールコーチとして活躍した村松尚登さんもこうおっしゃってます。
私は少し前まで、止まっているコーンを抜いていくようなドリル形式のトレーニングなどは、判断が伴わないその状況というものが試合中にはないのだから、やる意味がないのではないかとさえ思っていました。
それならばゲーム形式のトレーニングのなかでドリブルをやったほうがいいんじゃないか?
という考えがあり、極力ドリル形式のトレーニングを敬遠しているところがありました。
しかし、私はいま、指導している子どもたちにドリル形式のトレーニングの重要性も伝えています。 引用:ゲーム形式のトレーニングだけでは爆発的な成長はない⁉ 元バルサスクールコーチがドリル形式のトレーニングを取り入れる理由とは - サカイク
そこで、今回は、サッカーの初心者及び低学年対象のコーン(マーカー)ドリブルの練習方法とポイントをご紹介したいと思います。
コーンドリブルとは
サッカーでのコーンドリブル(ジグザグドリブル)とは一般的に、複数のコーンやマーカーを一定間隔に置いてジグザグにドリブルする練習のことを言います。指導方法にもよるのですが、ドリブルをする際、ボールタッチを指定することで様々なタッチを練習することができます。
コーンドリブルの練習方法の種類
ダブルタッチ
やり方は
- インサイドで止めます。
- 止めた足で斜め前に移動します。この時体全体で移動します。(足で動かすのではなく添えるだけのイメージ)
- 逆の足のインサイドで止めます。
- 繰り返し
ダブルタッチは足だけでやるやり方と、体全体で行うやり方があるのですが、体全体で行うやり方のほうが慣れれば早く移動できます。
ロールインサイド
やり方は
- インサイドで止めます。
- 止めた足の裏でボールを横に出します。
- 逆の足で止めます。
- 繰り返し
ダブルタッチとほぼ一緒ですが、横へ動かす際に足の裏で移動させます。
足だけでボールを動かすのではなく、これも身体毎動かすイメージです。
足だけでボールを動かすのではなく、これも身体毎動かすイメージです。
片足インサイド・アウトサイド
やり方は
- 全て片足で行います。
- 片足のアウトサイドで横へ移動します。
- 同じ足のインサイドで止めます。
- 同じ足のインサイドで移動します。
- 同じ足のアウトサイドで止めます。
- 繰り返し
アウトサイドで止める時に素早く体重を移動して動かないと足だけの形になってしまいます。
アウトサイド・インサイド・アウトサイド・インサイド
やり方は
- ボールを止める時はインサイド
- ボールを横に動かす時はアウトサイド
- 繰り返し
ステップとアウトサイドのタッチを速くすればするほど速くドリブルが出来ます。
子供達がやると、アウトサイドへ移行する時にインサイドの力が弱すぎて上手く出来ない場合があるので、最初はしっかりとインサイドでボールを次の動作に移しやすい所へ置くのがポイントです。
アウトサイド2タッチ
やり方は
- アウトサイドで移動します。
- 逆足のアウトサイドで止めます。
- 繰り返し
足の短い子供達にとってアウトサイドで移動してアウトサイドで止めるのはなかなか難しい動作であります。
気持ち遠目(ボールが転がる先)に足をつき素早く足を組み替えるのがポイントです。
アウトサイド1タッチ
やり方は
- アウトサイドで移動します。
- 体を大きくボールの外へ置き逆足のアウトサイドで運びます。
- 繰り返し
アウトサイドの2タッチと違い、体の動かし方が大事な練習となります。
しっかりと、横へ大きく踏み込まないと次の一歩が出ないので、いかにしてアウトサイドを行った後の1歩を踏み出すかがポイントです。
しっかりと、横へ大きく踏み込まないと次の一歩が出ないので、いかにしてアウトサイドを行った後の1歩を踏み出すかがポイントです。
アウトロール・ダブルタッチ
やり方は
- 舐めるようにアウトサイドで横へ移動します。
- アウトサイドで使った足で止めます。
- そして逆足で始まるダブルタッチを行います。
- アウトサイドで使った足で止めます。
- 繰り返し
ダブルタッチの応用になるのですが、単純にダブルタッチの前にアウトサイドで外側に舐めているだけです。
右足から始める場合は、
- 右足アウトサイドで右へ行く
- 右足で止める
- 左足のインサイドで横へ動かす
- 右足で止める
- 左足アウトサイドで左へ行く
といった形です。
足裏タップ
やり方は
- 左右交互に足の裏でボールをタッチしながら進む
ポイントは、交互に行うという点です。
片方だけ行うとボールを触っていない方の足が疲れてしまうので交互に行います。
2タッチシザース
やり方は、
- アウトサイドで2回タッチする
- タッチした足でシザースをする
- 直ぐに逆の足のアウトサイドで止め連続で2回タッチする
ポイントとしては、シザースの際に少し大きめに跨ぐことです。
そうすることで次のタッチが素早く出来るようになります。
指導ポイント
速さを常に意識させる
最初は確認しながら、そして徐々に早くするように促します。ある程度練習すれば各ドリブルの形はできると思います。
しかし、速さを意識しなければ単調になってしまい自身の限界は超えられません。
常に速さを意識させる声がけが重要です。
タッチを細かく
速さを求めていくと必然的に細かいタッチに行き着きます。そして細かくやることでタッチ数やステップが速くなり総合してボールコントロールと身体の動かし方が向上します。
顔を上げてできるようにする
マーカーやコーンがあると必然的に視線がそちらに向いてしまいます。それが癖にならないように、ステップを覚えたら視線を前に向けるように声がけをします。
飽きさせないように工夫
コーンドリブルは基本飽きやすく低学年は直ぐによそ見をしたりお喋りを始めたりします。色々なタッチの種類をやるのも大事なのですが、10分程で飽きてしまうので、様子を見て競争を入れると効果的です。
競争の方法は色々ありますが、リレー形式でも横一列での競争でも何でも良いです。
1位になったら名一杯褒めてあげましょう。
すると、次もう一回やるやる!っていう感じになります。
また、勝ったチームが次のタッチの指定を行えるようにするなどの工夫も飽きさせない上で大事です。
コーンドリブルのメリット
コーンドリブルでの練習によるメリット(成長する点)は大きく分けると2つあります。ボールコントロールが上手になる
一つ目は「ボールコントロールが上手になる」です。初心者のかたや低学年の子供達は、まだボールを扱うことに慣れてはおりません。
その為、足のどこに当たるとボールがどう転がっていくかなかなかイメージできないものです。
ボールマスタリーをやることである程度学習することができるのですが、最初は触ったボールの位置が不安定で理想と現実の差がわかりにくいです。
しかし、コーンドリブルは、コーンという目印があることで、ボールがどういった軌道で転がっていくかが分かり、修正しやすくなり練習効果が上がります。
身体の使い方が上手になる
コーンドリブルが上手に早くなるためには、ボールタッチも大事ではありますがそれ以上に素早いステップが重要となります。例えばインサイドで動かして次にアウトサイドで触らなければならない時、アウトサイドで触るには、身体を触る方の足よりやや外側に逆の足をつかなければ方向を変えることは出来ません。
こういったステップや身体の使い方を覚えることで、試合でのボールをもらう際のマークの外し方や相手を背負った形でのトラップに役立つのです。
コーンドリブルのデメリット
デメリットとしては、単調になりやすく子供達にとっては飽きやすいことでしょうか。このあたりは、チーム戦や個人戦などの競争できる要素を取り入れたり、コーンを倒したり、コーンとの距離を変えたりなどで対応することが可能です。
リレー形式で競争する際に、コーンドリブルの帰りにマーカーを頭に乗せ落とさずに帰ってくるとか、最後のコーンを倒してコーンの上を通すなどの要素を入れると盛り上がれます。
終わりに
今回ご紹介したメニュー以外にもマーカーやコーンを使ったドリブルは沢山あります。ドリブルが上手い子は、必ずといって良いほどコーンドリブルが正確で速いです。
また、自主練習としてもコーンドリブルは有効だと思います。
尚、マーカーは安くて持ち運びも簡単、しかも片付けやすいので個人的にはマーカーの方が好きです。
アジリティの練習と併用して行うとジュニア世代であるプレゴールデンエイジ・ゴールデンエイジの子供達はグングン伸びていくことでしょう。
スポンサーリンク

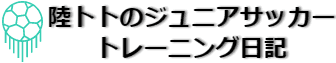







0 件のコメント:
コメントを投稿