特にサッカーを習いたての子は、ボールを常に追いかける傾向が強いと思います。
時には味方のボールを奪ったり(笑)
皆が皆ボールしか見ておらずボールに集まる…それが結果的にゴチャゴチャしてしまうお団子サッカーにつながるわけですが、ジュニア世代のお団子サッカーは必ずしも悪いわけではありません。
幼少期にお団子サッカーを経験することにより以下のメリットが得られます。
- ボールへの執着心
- お団子の中で突破するドリブル力
- 複数人でのプレスによる奪い方
- 攻守の切り替え能力
なので低学年のうちは、無理に脱お団子サッカーをする必要は無いのですが、お団子サッカーは身体能力、ドリブル力の差が出てしまい一人上手い子・強い子がいると全く勝てなくなってしまいます。
一番のピンチは、ゴールキック(スロー)ですね。
飛ばないので直ぐにゴールに直結してしまいます。
一番のピンチは、ゴールキック(スロー)ですね。
飛ばないので直ぐにゴールに直結してしまいます。
次に怖いのがセンタリングです。
お団子で群がった時にセンタリングされると高確率でゴールしてしまいます。
そんな状態で負け越しているチームもあるかと思います。お団子で群がった時にセンタリングされると高確率でゴールしてしまいます。
しかし、低学年でも比較的に簡単な守備のルールを作ることで失点を抑える事ができます。
それが「マーク」です。
今回は、小学校低学年でもできる守備の基礎である「マーク」についてご紹介したいと思います。
マークとは
マーク(Mark)とは守備時に相手選手に張り付き自由に攻撃させないよう行動を制限する守備行為である。マークを行っている守備の選手をマーカー(Marker)、マークすることをマーキング(Marking)と呼ぶ 引用:ディフェンス (サッカー) - wiki 最終更新 2016年11月1日 (火) 01:35
何故マークをしなければならないのか?
「マークはどうした!」
って怒鳴っているところもありますよね。
しかし、ただマークという言葉を教えると言っても、真面目な子はコーチの言うとおりに実行するかもしれませんが、ほとんどの子供たちは動かないし混乱してしまうだけでしょう。
理由としては簡単で「なぜマーク?」ということが理解していないからです。
子供達の本質は試合で勝ちたい!シュートを打ちたい!ボールに触りたい!ということがほとんどでありますので、そこを刺激してあげるのがベストであります。
極端な話「攻めるためにマークをする」と言った方が子供達はやる気になります。
ボールは人から人に渡っていくもの
ましてや勝手に転がって敵のゴールに入ることはまずありえません。
必ず、人から人へと渡って最後に誰かがゴールへ運んで入れるというのがサッカーです。
即ちマークをしておけば、より早く相手のボールを取る機会が増えるというわけです。
マークしてボールを奪えば点が取りやすくなる!シュートが打てる!ドリブルが出来る!守ることが出来るので試合に勝てる!
こういったポジティブなイメージで問いかけをします。
しかし、これだけではマークの意味や理由は分かったとしてもやり方までは解りません。
そのような状態で行うと以下のようになってしまいます。
小学生のあるあるパターン
細かいことを上げれば数多くあるのですが、大きく分けると3つあります。
ぴったりマーク
まずは恒例のぴったりマークです。
体と体をガチガチにぶつけ合い相手の進行方向を妨げるプレー。
常にゴール前の競り合いのイメージです。
ゴール前などでは、触られたら即1点の場面なので相手に自由にさせない意味でのマンマークは良いのですが、常にその状態だと相手の足が速ければ直ぐに裏を取られてしまいますし、進路妨害(インピード)を取られてしまいます。
そういった子は大抵次のパターンにも当てはまります。
そういった子は大抵次のパターンにも当てはまります。
相手しか見ていない
単純に「マーク=相手に付く」という言葉でしか理解出来ていない時、陥りやすく、まるで鬼ごっこのような動きをします。
相手しか見ていないので、ボールが来たとき反応することができなくボールを奪うことができません。
そして次のあるあるパターンに更につながっていきます。
相手しか見ていないので、ボールが来たとき反応することができなくボールを奪うことができません。
そして次のあるあるパターンに更につながっていきます。
身体の向きが逆
コーナーキックの際などで良くあるパターンで、相手ばかりを見るため相手の背後に隠れてしまい先にボールに触られ失点するといった形です。
マークの原則が分かっていないことにより発生してしまいます。
マークの付き方
マークの付き方は時と場合により若干の違いがありますが、覚えておかなければならない3つの原則があります。
サッカーでは、その原則に従って判断し動かなければいけません。
マークの三原則
マークの三原則とは一般的に以下のことを言います。- 自陣ゴールと敵の間の線上にポジションを取る
- インターセプト(パスカット)を狙える位置を取る
- ボールと相手を同一視出来る向きを取る
自陣ゴールと敵の間の線上にポジションを取る
守備の本質は相手からゴールを守ることです。
そのためには自分のゴールと相手の間に入らなければいけません。
基本的に、相手がボールを持った時にゴールに一直線で向かわれたり、前を向かれシュートされると最大のピンチになるため、そこを潰すためのポジショニングとなります。
インターセプト(パスカット)を狙える位置を取る
マークの理想は、インターセプトです。
相手より先にボールに触り、そのままカウンターというのが良い攻撃パターンとなります。
そのためには、インターセプトが狙える距離が大事となります。
相手と近ければ近いほどインターセプトが狙えるのですが、近すぎると裏のスペースを狙われてしまうので、近すぎず遠すぎずというのがポイントです。
特に逆サイドでは裏のスペースを使われる機会が多くなるため相手との距離は少しだけ開けておきます。
そのあたりも相手との足の速さなど駆け引きが大事です。
ボールと相手を同一視出来る向きを取る
相手とボールはプレー中に必ず動くものであります。
そのため、対象が動くと同時に上記のポジショニングがずれてしまうことになります。
そのギャップが一瞬のマークのハズレに繋がり致命的な失点となってしまうのです。
そこで、ポジションのギャップ(ボールと相手の動き出しに合わせて素早くポジションニングを調整)を埋めるため直ぐに修正出来るために行うのがボールと相手を同一視すること大事となります。
前を向かせない、または相手のプレーを遅らせる
マークの三原則を守った上で大事なのが、「前を向かせない、または相手を遅らせるプレー」です。
マークする相手から離れると確かに抜かれもしないし、裏のスペースも使われる可能性が減ります。
しかしながら、相手は前を向けてしまい距離があれば直ぐに次のプレーが出来てしまいます。その場合、ゴールに直結したプレーをされる可能性が高くなってしまうのです。
そのため、インターセプトが出来なくとも相手にボールを渡った時に振り向かせないことが相手のプレーを遅らせることにつながり、遅らせることによりフォワードの人が戻ったり周りの仲間がマークに付いたりといった相手のプレーを遅らせることにつながっていくわけです。
マークする相手から離れると確かに抜かれもしないし、裏のスペースも使われる可能性が減ります。
しかしながら、相手は前を向けてしまい距離があれば直ぐに次のプレーが出来てしまいます。その場合、ゴールに直結したプレーをされる可能性が高くなってしまうのです。
そのため、インターセプトが出来なくとも相手にボールを渡った時に振り向かせないことが相手のプレーを遅らせることにつながり、遅らせることによりフォワードの人が戻ったり周りの仲間がマークに付いたりといった相手のプレーを遅らせることにつながっていくわけです。
マークの付き方の原則
マークの三原則をまとめるとこんな位置になります。マーク対象者のゴールとボールの位置により優先順位が変わってきます。
ボールから距離が離れていればボールが来るまでに寄せることが出来ますので、優先順位は裏を取られない位置となります。
また、ゴールから近い位置となれば必然と距離が近くなります。
守らなければいけないことは「ゴールを入れさせない」であるため、必ずゴールとマークの間に位置づけを行うことが大切です。
ただし、チーム戦術や周りの状況によりマークする位置が変わってくるのも考慮しなければなりません。(ゾーンディフェンスやインターセプトを積極的に狙える相手陣地など)
「大事なのは原則を理解し、状況で各自で判断すること」です。
マークの練習方法
マークの基礎が分かったとしても、それいきなり実践で出来るほど簡単なものではありません。
そこでいくつかマークの練習方法を記載したいと思います。
そこでいくつかマークの練習方法を記載したいと思います。
1対1
通常の1対1ではありません。
開始のボールを受ける時に少し工夫を入れます。
- ゴールを2つ作ったグリッド上のコート外にパスの供給役を一人付けます
- 最初だけボールを受ける子を決め、パスの供給役はボールを受ける子に合わせてボールを出します
- 1対1を実施します
- 時間を30秒程度に区切り、それまでシュートを打たないとボールを受ける子の負けというルールです。
狙いとしては、攻め側はボールを貰う動き、そしてトラップの向きを意識しなければなりません。
守る方は、ゴールを入れられないように相手に付く(マーク)しなければいけません。
この練習を行うと自然にマークを意識するようになります。
出来るようになったら、連続で攻守を交代し直ぐに行うことで攻守の切替の早さを養えます。
3対3
3対3になるとより実戦向きの練習となります。
練習方法としては、
- オフェンスのゴールを1つ、ディフェンス側はサイドにコーンなどでゴールを2つ容易します。
- オフェンスの人数は3人、ディフェンスの人数はキーパー含めて4人
- ディフェンスからのキックインでオフェンスにボールを渡します。
- オフェンスは、組み立てながらゴールを狙っていきます。
- ディフェンスは、マークに付きながらインターセプトを狙ったりしつつ守ります。
- ボールを奪ったらサイドにあるゴールに目掛け組み立てパスします。
例学年の子供達は、なかなか同時に2つのことが出来ません。
しかし、この練習を行うことで試合の中で相手を見つつ守るということを学ぶことが出来ます。
あまりうまく出来なかった場合、一回走るのを禁止して行うと子供達の動きがよく分かるのでやってみると良いかもしれません。
あまりうまく出来なかった場合、一回走るのを禁止して行うと子供達の動きがよく分かるのでやってみると良いかもしれません。
パスゲーム
マークを意識できるようになってきたらパスゲームで楽しみながら練習します。
5対5位の人数でグリッドを用意し、その中でパスを回すゲームです。
ルールは、
- 10回パスを回されたら負け
- 相手に触られたりグリッドから出た場合、0から数え直し
子供達は負けない為に自ら考えマークするようになるでしょう。
終わりに
マークはサッカーの戦術を学ぶ上での基礎となる部分であり、サッカーの守備の第一歩です。
そして、マークを覚えることで自然に顔を上げてプレーをする大切さを学ぶ事ができます。
最初のうちは思うように動けない子供達が多数でしょうが、パスゲームなどの競争させる練習を組み入れることにより、徐々にできるようになるでしょう。
大事なのは、「なぜマークをするのか」を強制的ではなく遊びの中から自然と学ばせる事ができるかだと思います。
是非、チーム練習で取り入れてみてください。
スポンサーリンク

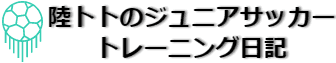









.jpg)
0 件のコメント:
コメントを投稿